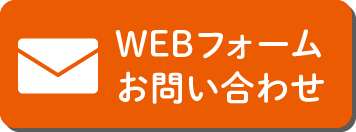モチベーションの源泉を見誤ると、組織が崩れる |「やる気」が見えない職場で、いま起きていること
「やる気がない人が、実は一番信頼されていた」
ある福祉施設の現場で起きた出来事です。朝礼では発言が少なく、レクリエーションにも消極的。周囲から「やる気がない」と思われていた職員Aさんが、実は利用者からの信頼が厚く、記録や申し送りも丁寧にこなしていました。夜勤明けにも関わらず、後輩にそっと声をかけるような気遣いをしていたのです。
ところがある日、そんなAさんが突然、退職を申し出ました。「どうして?」と施設長が聞いたところ、「頑張っても評価されない。やる気がない人だと思われていたみたいで…」と、ぽつり。
誰よりも真摯に向き合っていた職員が、正しく評価されないまま辞めてしまう――これは氷山の一角です。
あなたの職場でも、似たような兆候はありませんか?
「やる気があるように見える人」が優秀とは限らない
印象評価に潜む危うさ
「笑顔で元気な人がいい」「積極的に発言する人が伸びる」――そう信じていませんか?
確かにそれも一つの資質ですが、それだけで評価を決めてしまうと、本来の力を発揮している人を見逃してしまいます。
実際、ある介護施設では、「元気に話す」「常に前向き」を基準として、一般職員の評価内容を大幅に見直しました。
その結果、無理にテンションを上げるスタッフが増え、現場の空気がぎこちなくなり、数ヶ月後には3名の中堅職員が辞職。
職場のバランスが崩れ、業務に混乱をきたしたのです。
ESサーベイの数字に振り回されていませんか?
また、スコアを上げるための“演技”が始まっているかもしれません
ES(従業員満足度)サーベイのスコアを追いかけるあまり、現場に「空気を読む回答」が蔓延する事例も少なくありません。
ある医療法人では、毎年実施しているESサーベイで急激な点数向上が見られたにもかかわらず、翌年の離職率が過去最悪を記録しました。
その原因は、「低評価を出すと自分の部署の責任者が評価を下げられる」と思ったスタッフが、忖度回答をしていたこと。結果として、問題が可視化されず、改善機会を逃してしまいました。
あなたの職場でも「サーベイのスコアが良いから大丈夫」と安心していませんか?
やる気は「見える」時代から「感じる」時代へ
若手職員の“静かなやる気”を見逃していませんか?
最近では、職場内での「やる気アピール」が苦手な職員も増えています。特に20代の若手職員は、無理に自分を主張せず、仕事で結果を出すことを重視する傾向があります。
例えば、ある特養の新人職員Cさんは、おとなしく寡黙で、会議でもほとんど発言しませんでした。
ところが、利用者の介助記録を丁寧に読み込み、対応の工夫を重ね、ある日ベテラン職員さえ気づかなかった転倒リスクを事前に察知して対応。大事には至りませんでした。
発言しないからといって、関心がないわけではありません。
「見えるやる気」だけで職員を評価することの危うさが、ここにも現れています。
モチベーションの源泉は人それぞれ
制度や評価では掴めない「想い」がある
「この人、本当にやる気があるのかな?」
そう思ったとき、その人がどうして今の仕事をしているのか、質問したことはありますか?
あるパートスタッフは、「週3日でも、利用者の“ありがとう”が聞きたくて続けている」と話していました。
別の常勤職員は、「亡くなった祖母が入居していた施設で働きたいと思って」と、静かに語りました。
これらの動機は、数値化やランクづけでは測れません。しかし、組織にとってかけがえのない“熱源”です。
制度設計だけでモチベーションは支えられない
評価制度の導入で失敗するケースも
「評価制度を導入すればやる気が上がる」と期待して、就業規則や人事評価を整備したものの、かえって職員のモチベーションが下がった、という相談も増えています。
制度が「成果主義」に偏りすぎたり、「加点主義」が行き過ぎたりすると、現場では「誰の顔色をうかがえば評価されるか」が主軸になってしまいます。
人事評価制度は必要です。
しかし、それは個々人のやる気を引き出すためだけではなく、すでにある“火種”を守り、そっと風を送るものだと、私は考えています。
【トラブル事例】「やる気がない職員を放置した結果…」|実際に起きた、組織崩壊のきっかけ
ある小規模の介護施設では、「やる気がない」とレッテルを貼られていた職員Dさんに対し、上司が「このままだと減給する」「評価を下げる」と繰り返し圧力をかけていました。
Dさんは、職員のタイムカードの集計作業など、裏方の重要業務を丁寧にこなしていた人物です。
結局、彼はメンタル不調で休職。記録管理が滞り、給与計算業務のミスが発覚。最終的には監督署からの監査の結果、数十万円の未払い残業代返還命令が下され、法人の経営に大きな影響を与えました。
誰もが「こんなに影響が出るとは思わなかった」と語りましたが、その根本には「やる気が見えない=評価対象外」という、短絡的な判断がありました。
社労士事務所としての見解
モチベーションを「仕組み」と「信頼」で支える
当事務所では、評価制度や労務トラブル対応だけでなく、「やる気の見え方」に悩む管理者のご相談を多くいただきます。
制度導入を検討する際、「この制度が職員の“火”を消さないか?」という視点を必ずご提案に組み込みます。
また、「やる気があるように見える人」ばかりが得をする評価体系から、地道に貢献している職員が報われる仕組みへと再設計する支援も行っています。
“やる気の見え方”の誤解が、組織崩壊の第一歩
一見、問題なさそうに見える職場にも、「静かなSOS」が潜んでいることがあります。
「評価されない」「理解されない」「やる気がないと思われている」――そんな想いが募ると、ある日突然、優秀な人材が離れていく。
その時に「もっと早く相談していれば…」と後悔しても、失った信頼と損失は戻ってきません。
職員のモチベーションや評価制度、ESサーベイの運用にお悩みの方へ。
当事務所は、現場のリアルな声に耳を傾け、経営者や人事担当者の「困った」を具体的な仕組みに変えるサポートを行っています。
「このままだと少し危ないかもしれない…」
そう思った今が、対策の第一歩です。