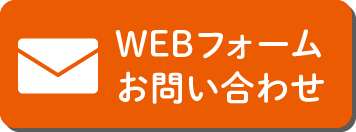現場にあるさりげない多様性――事業所で紡がれるD&Iと交流のかたち
※本記事に登場する人物・企業名は、すべてプライバシー保護の観点から架空のものです。ただし、記載されている事例は、当事務所が実際に経験した複数のケースを基に再構成したものであり、その本質は実際の経験に基づいています。
ふとした現場の会話に、“職場の空気の質”があらわれることがあります。
「最近の若い子にしては、よう笑う子やねぇ」
そう話したのは、入所して2年になる90歳の竹田さん。
視線の先には、1年前に入職したばかりの介護職員、リンさんの姿がありました。
リンさんは、ベトナムから技能実習制度を利用して来日した職員です。日本語はまだ不完全ながらも、常に明るく、誰に対してもまっすぐに向き合おうとする姿勢が印象的でした。
「リンさん、ありがとう。寒いねえ、外は」
竹田さんの言葉に、リンさんは少し訛った日本語で笑顔を返します。
「はい、さむいです。でも、ここ、あたたかいです」
たどたどしいやり取りの中にも、心がふっとゆるむような空気が流れました。
一見、和やかな日常ですが――もしこの“空気”がなかったら?
私たちが相談を受ける中でよく耳にするのは、「制度はあるのに職場が噛み合わない」「新人が定着しない」といった声です。
もしかしたら、その違和感は“見えない孤立”のサインかもしれません。
このコラムでは、ある特別養護老人ホームの事例を通じて、「制度」でも「マニュアル」でも生まれない、“交流から育つ多様性”の姿をたどります。
もし今、あなたの事業所で「何かがちぐはぐだ」と感じているなら、どうか読み進めてみてください。
目次
Toggle特養という、静かでにぎやかな交差点
特別養護老人ホームは、介護が必要な高齢者が長期的に生活する“暮らしの場”です。そこには、利用者と職員、世代も文化もさまざまな人々が関わり合いながら過ごしています。
この施設でも、20代の新卒職員から、子育てと両立している30代パート、定年後に再雇用された60代のスタッフ、そして外国人技能実習生として働くリンさんといった、多様な人たちがともに働いています。
ここでは、現場で自然に育まれている“違い”と“交流”の風景をご紹介します。
世代を超えたまなざし――ベテラン職員と若手の気づき
ある夜勤での出来事です。認知症のある利用者が混乱し、大きな声を上げる場面がありました。
慌てて駆け寄ったのは、再雇用で働く佐藤さん(67歳)と、ベトナム出身のリンさんでした。
「大丈夫です」と落ち着いて対応するリンさんを見て、佐藤さんはふと呟きました。
「…昔の私を見てるようだわ。でも、私より丁寧よね」
その言葉には、年齢や経験を超えた“尊敬”の気持ちが込められていたように感じました。
育児との両立と、若手職員のまなざし
パート職員の大西さん(30代)は、2人の子どもを育てながら日中の短時間勤務をしています。
ある日、保育園のお迎えがあるために早退する彼女に、若手の田中さん(22歳)が言いました。
「お子さん、元気ですか?何か手伝うことあれば言ってくださいね」
背景の違いに“気づく”ということ。
そのちょっとした一言が、職場の温度を変えていきます。
外国人職員との関係は「一緒に働くこと」から生まれる
リンさんは、日本の介護現場での経験は初めてでした。
最初は「日本語が通じにくい」と距離を取っていた職員も、日々の丁寧な対応に触れ、次第に心を開いていきました。
「言葉より、伝えようとする気持ちが大事なのかもしれませんね」
ある職員のこの言葉が、現場の空気を変えるきっかけになりました。
ささやかな交流が、職場を変える
D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)という言葉を、あえて声高に掲げなくても、現場によっては、日々自然に“違いに触れ、受け止め、交わる”営みが繰り返されます。
ここでは、実際の現場で育った、ささやかな交流の事例をご紹介します。
言葉の壁を越えた安心感
排泄介助の場面で、リンさんはいつもより少し時間をかける傾向がありました。
あるとき、急いでいた先輩職員が「もう少し早くお願い」と声をかけたことがありました。その後、利用者から届いた言葉はこうでした。
「今日のトイレは安心やった。時間かかってもええねん」
そのひとことに、先輩職員はハッとしたようにリンさんへ頭を下げました。
“早さ”だけでは測れない価値が、確かにそこにありました。
「料理」がくれた共通点
ある日の休憩時間、リンさんが「ベトナムの春巻き」をスマホで見せながら話していたときのことです。
「へえ、こんな感じなんだ!おいしそう!」
「うちの近所にベトナム料理屋さんあるよ、今度一緒に行かない?」
そんな一言から、“持ち寄りランチ会”が始まりました。
手作りの家庭料理を囲みながら、文化や日常を自然に語り合える時間。
それは、勤務中には見えない「素の顔」が出会う、貴重な交流の場となっています。
「ちがい」をおもしろがる気持ち
職場のホワイトボードに書かれた、さりげない質問――
「ベトナム語で“ありがとう”ってどう言うの?」
それにリンさんが「Cảm ơn(カム・オン)」とふりがなとメモを添えて答えた日、
「なんて読むの?」「発音むずかしいなー」と、周囲から笑い声が広がっていきました。
“違い”を怖がるのではなく、おもしろがれる空気。
その空気こそが、職場の土壌を豊かにしていくのだと感じました。
制度と空気が、土台を支える
多様な人が働く職場では、「関係性」が最も大切――そう感じられる一方で、それを支える「制度」も欠かせません。
ただし、制度は“ある”だけでは不十分です。職場の空気に根づき、使われてこそ意味を持ちます。
制度があることで、ようやく声を出せる
この施設では、外国人職員向けにやさしい日本語で書かれた就業ルール集を準備しています。
また、評価面談の際には通訳者が同席するなど、意思疎通のサポート体制も整えられています。
「不安で言い出せない」「間違っていたらどうしよう」
そうした躊躇を超えるには、「制度がある」という安心感がまず必要です。
家庭や背景に配慮する“柔らかい制度”
子育て中の職員や、親の介護をしている職員に対して、勤務シフトの希望や相談を柔軟に受け付けています。
中でも評価されているのが、「希望を出しやすい空気」の存在です。
「申し訳ない」ではなく、「ありがとう」と言い合えること。
それが、働きやすさのベースとなっています。
制度の“温度”を決めるのは、現場のまなざし
制度の文言以上に大切なのは、それを“どう運用するか”です。
たとえばリンさんが有給休暇を申し出た際、先輩職員はこう言いました。
「どうぞ、リフレッシュしてくださいね。お土産話、楽しみにしてるよ」
制度があるだけでは、こうはなりません。
制度を“使えるようにする空気”をつくる――それは、現場の誰かのまなざしなのです。
まとめ:違いが響き合う職場づくりのヒント
医療や介護、福祉の現場では日々「多様性」が息づいています。
病院といった医療機関や特別養護老人ホーム、障害者施設のような施設は、その縮図といえる存在です。
今回のコラムでは、ベトナムから来たリンさん、再雇用の佐藤さん、育児と両立する大西さん、そして若手の田中さんが、それぞれの背景を持ちながら“ともに働く”ことを通じて、自然に交流を深めている事例をあげてみました。
小さな声かけが、空気を変えていく
「大丈夫?」と声をかける
「ありがとう」と丁寧に伝える
「どうしてる?」と関心を持つ
たった一言の積み重ねが、“違い”を“壁”ではなく“可能性”へと変えていきます。
制度やマニュアルよりも、まずは「誰かに関心を持つこと」が出発点なのだと思います。
“文化”としてのD&Iを育てる
制度は土台です。しかし、それを活かすのは、日々の空気と関係性です。
「声をかけやすい」「相談しやすい」「無理しすぎなくていい」
そんな空気があるからこそ、制度は“効く”のです。
当事務所では、就業規則や評価制度の整備とあわせて、「その制度が現場でどう響くか」「誰を励まし、誰を黙らせていないか」にまで目を向けた支援を行っています。
“制度設計=文化設計”という視点での支援――それこそが、これからの社労士に求められている役割ではないでしょうか。
“違和感”を抱いたときこそ、見直しのチャンスです
介護や医療の現場は、日々の業務に追われがちで、足元を見直す時間がなかなか取れないかもしれません。
でも、ふとした瞬間に感じる「最近ちょっとギスギスしてきたかも」「なんとなく新人が続かない」
そうした違和感こそ、見直しのチャンスです。
制度を整え、空気をやさしく温め直すだけで、職場は確実に変わります。
それを、ひとりで悩む必要はありません。
当事務所では、現場の声を丁寧に拾いながら、「制度と空気のちょうどいい接点」を一緒につくるサポートを行っています。
まずは小さなきっかけからでも構いません。
「何か、合ってない気がする」その直感を、どうか見過ごさないでください。