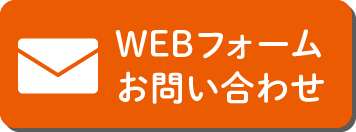外国人技能実習生と訪問系サービス(3)|実際の運用における留意点と共生する職場づくり
制度は整いました。申請手続きも整備されました。しかし、ここからが本番です。
訪問介護という生活空間に密接に関わる業務において、外国人技能実習生が“本当に活躍できる”環境をつくるには、紙の上では語れない現場の視点が必要です。
本稿では、実際に技能実習生が訪問系サービスに従事する際の現場対応や、経営者・人事担当者が今こそ意識すべき「共に働く場」のあり方について考察します。
実務上のキーワードは「説明」と「準備」
訪問系サービスでは、利用者宅という閉じられた空間に単独で入る業務も想定されます。
そのため、技能実習生の受け入れにあたっては、「制度で認められているから大丈夫」では済まされません。
まず重要なのは、利用者や家族への丁寧な説明です。技能実習生が訪問に入る理由、経歴、サポート体制などをあらかじめ誠実に説明し、不安を取り除くこと。それが信頼の第一歩になります。
同時に、実習生本人に対しても、「このご家庭ではこういった文化・習慣がある」「こういう緊急事態が起こる可能性がある」といった具体的な事前情報の共有と準備が求められます。
単独訪問への段階的アプローチ
制度では、一定の実務経験や研修を経た実習生であれば単独訪問も可能とされていますが、現場での運用は慎重であるべきです。
いきなり「単独訪問に出す」のではなく、
最初は同行支援で現場を体験
訪問先ごとに段階的に慣れていく
定期的に振り返りの時間を設ける といったフェーズごとの計画と、職員間の共有が不可欠です。
ここでカギを握るのが「チームとしての支援体制」。
単なるマンツーマンの指導で終わらせず、職場全体が実習生を理解し、支え合う文化を育てていく視点が重要です。
異文化コミュニケーションは“摩擦”ではなく“機会”
異なる文化背景を持つ技能実習生が現場に入ると、当然ながら考え方や価値観の違いに直面することがあります。
「言われたことしかやらない」
「報告が遅れる」
「日本語の細かいニュアンスが伝わらない」——
こうした場面で苛立つのではなく、「どう伝えれば伝わるか」「なぜその反応をするのか」と、“違い”を掘り下げていく姿勢が問われます。
異文化コミュニケーションとは、ただ我慢することでも、相手に合わせることでもなく、互いの前提を開示し、理解し合うプロセスです。
それは決して容易ではありませんが、職場全体のコミュニケーションの質を引き上げる契機になるはずです。
ハラスメントの芽を摘む「空気のデザイン」
言語や文化の違いは、ハラスメントの温床にもなり得ます。「悪気がなかった」「冗談のつもりだった」という言葉では済まされません。
特に訪問介護の現場では、職場の目が届きづらいため、孤立感や不安が増幅しやすい状況にあります。
当事務所では、形式的なマニュアルだけではなく、
定期的な面談や振り返りの時間を設ける
メンター制度の導入
感情の共有を重視した職場内研修 といった、「空気を整える」工夫が今後の鍵を握ると考えています。
経営者が持つべき視座とは
現場職員に任せきりにしていては、この制度は“続かない”でしょう。外国人技能実習生が単に「手が足りないときだけの存在」になれば、職場内に分断を生みます。
経営者こそが、
自社の介護事業の価値観とビジョンを明確にし、
それを全職員と共有し、
外国人実習生にも“仲間”として期待する姿勢を示す
この姿勢があって初めて、制度が持つ可能性が現場で活かされるのです。
当事務所としての見解
「制度に従って手続きさえすればいい」
その発想は、もう時代遅れになりつつあります。
訪問系サービスという、繊細で対人関係に重みのある現場に外国人技能実習生を迎え入れるということは、単なる制度対応を超えた“組織の器”が問われるということです。
当事務所では、制度そのものよりも、制度を通じてその組織がどのような文化を育むかにこそ、真の価値があると考えています。
今後、介護・障害福祉の分野では、国籍や言語に関係なく、誰もが尊重され、力を発揮できる現場が競争力の源泉になる時代がやってきます。
この制度をきっかけに、経営者・人事担当者の皆さまが、自社の“働く場のあり方”を再確認し、再定義されることを心から願っています。
【参考サイト】公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)|外国人介護人材関連ページ
【参考資料】「令和6年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 (資料8)福祉基盤課福祉人材確保対策室」(厚生労働省ホームぺージ)参考資料64(123頁下部~125頁)参照