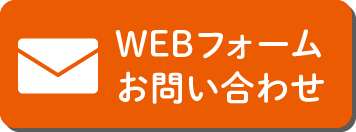外国人技能実習生と訪問系サービス(2)|適合確認書の取得と現場で求められる備え
制度が「認める」だけでは、本当のスタートにはなりません。
外国人技能実習生が訪問系サービスに従事するためには、受け入れる事業所側が制度上の要件を正しく理解し、適切な申請と準備を整える必要があります。
今回の第2回では、制度運用の要となる「適合確認書」の取得方法や、申請における留意点について、実務者の視点から詳しく解説していきます。
【参考サイト】公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)|外国人介護人材関連ページ
「適合確認書」とは何か?
制度上、外国人技能実習生が訪問介護等の業務に就くには、単に「実務経験がある」だけでは足りません。
実習実施者(介護事業所や監理団体)が、巡回訪問等実施機関からの確認を受け、「この事業所は、訪問系サービスに技能実習生を適切に従事させられる体制を有している」と証明されなければなりません。
この確認結果を示すのが「適合確認書」です。
言い換えれば、この確認書は訪問介護業務における“許可証”のような位置づけであり、制度上のハードルであると同時に、利用者や行政に対しての「信頼の証」にもなります。
【参考サイト】公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)|適合確認申請方法・提出書類
申請の流れ:ポイントは“準備と誠実さ”
適合確認書の取得には、いくつかの段階的なプロセスがあります。
一見煩雑にも見える手続きですが、その本質は「技能実習生が安心して訪問業務に従事できる体制を、事業所が備えているか」を丁寧に確認する作業です。
実習実施者または監理団体が行う申請の主な流れは次のとおりです。
専用のフォームにて「適合確認申請」を提出
必要書類(キャリアアップ計画、ハラスメント対策、緊急連絡体制など)を添付
巡回訪問等実施機関が内容を審査
問題がなければ「適合確認書」が発行される
この一連のプロセスは、書類さえ整っていれば簡単に通るというものではなく、むしろ事業所の理念や運営姿勢が問われる局面でもあります。
提出書類の中身を「単なる形式」と思わない
特に注意すべきは、提出する各書類の内容です。中でも「キャリアアップ計画書」は、技能実習生本人の署名を必要とし、彼らがどのようなステップを経て成長し、就労を続けていくのかという「未来」を描くものです。
また、「ハラスメント対応マニュアル」や「緊急時対応フロー」は、職場内の文化や意識の成熟度を反映する鏡のような存在です。
ここに、「実習生をどう守るか」「どう育てるか」「何を大切にしているか」が滲み出るのです。
制度対応を“義務”と受け取るか、“価値づくり”と捉えるかで、作成される書類の厚みがまったく違ってくるはずです。
同行支援の重要性と現場の感覚
今回の制度改正では、訪問系サービスへの従事にあたり、「同行支援」が不可欠とされています。
この“同行支援”とは、要するに「現場でのOJT」であり、単独での訪問を前提とするのではなく、実務に慣れるまでの間、ベテラン職員が付き添いながら業務を進めていくスタイルです。
しかし、同行支援はただの“引率”ではありません。
利用者宅というプライベートな空間で起きうる多様な事象――たとえば、生活習慣や宗教的な慣習、予測不能な緊急事態――を、外国人実習生がどう捉え、どう動けるかを共に確認しながら進めていく必要があります。
そこにこそ、同行者の力量と組織の成熟度が表れるのです。
「技能実習=人手補填」では終わらせない
忘れてはならないのは、今回の制度が「人手不足を埋めるための延命策」ではないということです。
確かに、目の前の人手不足にとっては福音に映るかもしれません。しかし制度の本質は、実習生一人ひとりの生活や成長と向き合う「受け入れ文化」の醸成にあります。
本来、制度に求められているのは
実習生が適切な支援のもとで成長できる環境を用意し、
利用者に対しては質の高いサービスを継続的に提供する、 という、二つの軸を丁寧に整えることです。
当事務所としての見解
今回の改正は、ただの制度対応で終わる話ではありません。
むしろ問われているのは「経営者や現場責任者の哲学」そのものです。
事務所としては、介護・福祉の現場における外国人材の受け入れを、「コスト」ではなく「投資」として捉える視点が不可欠であると考えています。
そのためには、マニュアルや様式を整えるだけでなく、現場の空気感、人間関係、意思疎通の質までもが問われる段階に来ているのです。
「適合確認書」はあくまでスタートラインにすぎません。
本当に求められているのは、文化の違いや言語の壁を越えて、外国人技能実習生を仲間として迎え入れられる職場の成熟度です。
【参考サイト】公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)|外国人介護人材関連ページ
【参考資料】「令和6年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 (資料8)福祉基盤課福祉人材確保対策室」(厚生労働省ホームぺージ)参考資料64(123頁下部~125頁)参照