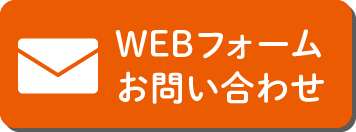介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策の全体像とその重要性(2)
「このままでは、職員がもたないかもしれない。」そう感じる介護施設経営者は、少なくないのではないでしょうか。
夜勤明けのスタッフが疲れた表情で「大丈夫ですよ」と笑顔を作る。管理者はなんとか離職を防ごうと励まし、シフト調整に頭を抱える。しかし、余裕のない職場環境は、介護の質にも影響を及ぼしてしまう。
「せめて、もう少し時間があれば……」「少しでも、業務が楽になれば……」
介護現場に長く携わっている人なら、一度はそう思ったことがあるはずです。
2024年度補正予算による「介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策」は、そんな現場の負担を軽減し、働き続けやすい環境を作ることを目的とした、介護事業者にとって非常に重要な施策です。ただし、これらの支援は 早めに準備しないと活用できません。
前回では施策の全体像をお伝えしましたが、今回は具体的な取り組みをさらに掘り下げ、それぞれの事業が経営にどのように活かせるのかを詳しく解説します。
介護業界で起こりうるトラブル事例
事例①:慢性的な人手不足が原因で、事業縮小に追い込まれたケース
ある介護施設では、人手不足が深刻化し、夜勤スタッフが次々と退職。管理者はシフトを回すために職員へ無理な勤務を強いることになり、最終的には過労が原因で事故が発生。施設の評判が悪化し、新規採用も難しくなりました。
結果:施設の信頼低下→人材不足が加速→事業縮小を余儀なくされる
事例②:補助金活用を知らずに、経営悪化が加速したケース
他の施設が最新の介護テクノロジーを導入し、業務効率化を進める中、この施設は補助金を活用しなかったため、職員の負担が軽減されず、離職率が増加。
結果:競争力が低下し、利用者数が減少。収益悪化でサービスの質も低下する負のスパイラルに。
1. 介護人材確保・職場環境改善等事業(予算:806億円)
「人が足りない」「疲れが取れない」——。
これらの課題は、単に給与の問題だけでは解決しません。
今回の施策では、「働き続けやすい環境づくり」にも重点が置かれています。
職員の負担を減らすためにできること
介護助手の導入支援
介護職員がすべての業務を担う必要はありません。介護助手(環境整備や食事準備、記録補助などを担当)を採用することで、職員の負担を分散できます。シフト見直し・勤務環境改善の補助
「夜勤が多すぎる」「長時間労働が常態化している」といった状況を改善するため、シフト再編や休憩時間の確保に必要なコストが支援されます。職場環境改善のための施設整備
休憩室の設置や更衣室の改装など、職員の働きやすさを向上させる取り組みにも補助が出ます。
「職員が長く働ける環境を作ること」
これは、結果的に利用者へのサービス向上にもつながります。
2. 介護テクノロジー導入・協働化等支援事業(予算:200億円)
「テクノロジーを入れても、本当に役に立つのか?」
そう思う経営者もいるかもしれません。確かに、ロボットやICT機器は導入にコストがかかります。
しかし、適切に活用すれば、職員の負担軽減に大きく貢献できます。
活用できる補助内容
見守りセンサーの導入
夜間の巡回を減らし、職員の負担を軽くする。移乗支援ロボットの活用
職員の腰痛リスクを減らし、介護の安全性を向上させる。記録業務のデジタル化
紙ベースの業務を減らし、事務作業の時間を短縮する。
小規模施設でも活用できる
「うちは小規模だから、ロボットなんて導入できない」と思うかもしれません。しかし、今回の施策では、地域内の複数事業所が共同で導入する場合、追加の補助が受けられる仕組みになっています。例えば、「地域で統一したICTシステムを導入し、事業所間の連携をスムーズにする」ような活用が可能です。
テクノロジーの導入は、単なる業務効率化ではなく、職員の負担を減らし、より良い介護サービスを提供するための手段ではないでしょうか。
3. 訪問介護の提供体制確保支援(予算:90億円)
「一人で訪問介護に行くのは、最初は本当に心細かったんです。」新人ヘルパーがそう打ち明けるのは、訪問介護ならではの難しさがあるからです。
施設介護と違い、訪問介護は一人で利用者の自宅を訪問し、適切なケアを提供する仕事。しかし、未経験の職員がすぐに自信を持って訪問できるわけではなく、「慣れる前に辞めてしまう」ケースも少なくありません。さらに、中山間地域や離島では、訪問先までの移動の負担も大きくなり、事業所の運営自体が厳しくなることもあります。
こうした訪問介護の継続的な運営を支援し、人材定着を図るために、今回の施策では次のような取り組みが支援対象となっています。
訪問介護を続けやすくするための施策
新人ヘルパーが安心して働けるように、同行支援を強化
- いきなり一人で訪問させるのではなく、ベテラン職員と一緒に訪問し、利用者との接し方やケアの方法を学べる体制を整える。
- これにより、「いきなり現場に放り出される不安」がなくなり、長く働きやすくなる。
訪問介護事業所の安定した経営を支援
- 訪問介護の担い手が不足している中山間地域や離島では、地域の特性に応じた柔軟な支援が行われる。
- 例えば、地域ごとに事業所間で協力しながら人材をシェアする取り組みも検討されている。
ホームヘルパーの魅力発信
- 「訪問介護=大変な仕事」というイメージを払拭するため、ヘルパーとしてのキャリアの魅力を広く伝える取り組みが支援対象に。
- 介護職としてのやりがい、訪問介護ならではの良さを発信することで、新たな人材確保を促す。
訪問介護は、「自宅で暮らし続けたい」と願う高齢者にとって、なくてはならない存在です。しかし、人材不足が深刻化すれば、利用者に必要なサービスが届かなくなる可能性があります。今回の支援策は、訪問介護の提供体制を守るための施策です。
当事務所の見解|対応しない場合のリスク
今回の補正予算は、単なる一時的な支援ではなく、介護事業の未来を左右する重要な機会です。
今、経営者がどう動くかによって、職員の定着率やサービスの質、事業の持続性が大きく変わってくるでしょう。
特に、以下の3つの視点が重要になります。
- 施設の環境改善を進め、職員が安心して働ける職場をつくる
- テクノロジーの導入を検討し、業務負担の軽減と効率化を図る
- 訪問介護の支援を活用し、人材確保と安定したサービス提供の基盤を築く
しかし、活用しなければ、
✅ 人手不足が悪化し、事業の持続が困難になる
✅ 競合施設が補助金を活用する中、自社は人材確保が難しくなる
✅ 業務負担が増加し、職員の離職が加速する
✅ 行政対応が遅れ、法令遵守の問題に直面する
といったリスクが生じる可能性があります。
ただ、頭では「やらなければ」と分かっていても、実際にどこから手をつければいいのか悩む経営者も多いはずです。
「人手不足を解消したい」「職員の負担を減らしたい」「経営の安定を図りたい」――そう考えつつも、具体的な施策に落とし込めずにいる施設も少なくありません。
この補正予算をどう活かせるのか、何を優先して取り組むべきか。当事務所では、そうした課題に向き合う経営者の皆様に、職場環境改善のアドバイスや制度活用のサポートを提供しています。
「現場をより良くしたいが、何から始めるべきかわからない」
職員が無理なく働ける環境を整えることは、結果的に利用者の満足度向上にもつながります。この機会をどう活かすか。未来を見据えた経営の一歩を、今から考えていきましょう。